本稿は、“Dissonant Death Metal”(不協和音デスメタル)という括りで近年広く認知されるようになってきた先鋭的なメタルの系譜およびその周辺(デスメタルに限らない)を俯瞰的にまとめたものである。こちらの記事でもふれたように、80年代末から90年代頭にかけて下地が築かれた“テクニカルスラッシュメタル”や“プログレッシヴデスメタル”などのシーンでは、定型化した以降のフュージョンなどが持て余していた高度な楽理や演奏技術に表現上の説得力を持たせた個性的な音楽が追求され、様々な形で素晴らしい成果が生み出されてきたのだが、それらを系統立てて語る言説は十分に確立されているとは言い難い。歴史的名盤であっても一般に知られていないものが殆どだし、この領域をそれなりに知る者でも、最初期のレジェンドの名前(DeathやCynic、Gorgutsなど)のみを挙げて新しいバンドの音楽性や影響関係を云々していることが非常に多い。初期デスメタル(Old School Death Metal=OSDM)リバイバルやプログデスといった系譜で括るのが適当でない領域が拡大し続けているにもかかわらず、それを語る批評の観点や表現がいつまでも更新されずにいるのは好ましいことではなく、活発に新陳代謝を繰り返すシーンの実情とその認知状況との乖離がどんどん大きくなっていってしまう。そうしたことを踏まえた上で、この記事は、上記のようなシーンの現状を把握するための見取り図を描くことを目的としている。不十分な部分も少なからずあるだろうし、これを叩き台としてさらに充実した論を構築していただけると幸いである。
参考記事:
closedeyevisuals.hatenablog.com
closedeyevisuals.hatenablog.com
closedeyevisuals.hatenablog.com
【まずはここから】本流を把握するための10枚
Gorguts:Obscura(1998)

このジャンルにおける最重要アルバム。ペンデレツキやショスタコーヴィチなど無調寄り近現代音楽の要素をテクニカルデスメタルの形式に落とし込んだ大傑作で、奇怪なフレーズやコード感に異常な必然性と説得力を持たせる作編曲が素晴らしい。演奏表現力もサウンドプロダクションも極上で、複雑な構造を細部まで快適に見通すことができることもあってか、デスメタル領域のみならず現代ジャズ(Dan Weissほか)など様々な方面に絶大な影響を与えている。実は1993年には殆ど完成しており(デモ音源集『...And Then Comes Lividity / Demo Anthology』で聴くことができる)、1998年の発表当時ですら時代の数歩先を行っていた(異形すぎる音楽性を歓迎しない反応がデスメタルファンの中にも多かった)このアルバムが順調にリリースされていたら音楽史はどんなふうに変わったのだろうか、と考えさせられてしまったりもする。メタルの歴史において最も魅力的な謎に満ちた作品の一つである。
Immolation:Close to a World Below(2000)

Immolationは初期デスメタルを代表するバンドの一つで、曲構成(特にコード進行)の抽象化傾向を先導する歴史的傑作を数多く発表してきた。本作は第2のキャリアハイとなった名盤で、後発組であるGorgutsなどの和声感覚を通過した上で独自の音楽性をさらに発展。激しさをあえて抑えたリズム構成や演奏表現も相まって、真似しようのない極上の旨みが生まれている。「不協和音デスメタル」というジャンル名で括られうるものの中では最も聴きやすいアルバムの一つだと思われるし、これを入門編とするのもいいかもしれない。
Today Is The Day:Sadness Will Prevail(2002)

Today Is The Dayは豊かすぎる音楽性もあってかジャンルの狭間に落ち込んでしまい十分な評価を受ける機会を逃してきたバンドである。DeathやSlayer、Morbid Angelといったスラッシュメタル~初期デスメタルを主な影響源とする一方で、MelvinsやButthole Surfers、UnsaneやThe Jesus Lizardといったハードコア寄りの越境的バンドからも多くを得ており、一言で表すのは殆ど不可能な広がりがある。本作はそうした音楽性を2時間半弱の大ボリュームに詰め込んだ代表作で、デスメタルからカオティックなハードコア経由で優美な初期ポストロックに接続するような混沌ぶりが凄まじい。アルバム全体としての構成はあまり解きほぐされておらず、その点においては欠陥の多い作品と見れなくもないのだが、その歪な形状自体が優れた表現力を生んでいる面も確かにあり、良くも悪くも唯一無二の魅力を湛えた傑作になっている。後続への影響力も絶大。メタル界最大のデータベースサイトMetal Archivesに登録を拒否されているのが信じられない重要バンドである。
Ulcerate:Everything Is Fire(2009)

現代の“不協和音デスメタル”を代表するバンド。ImmolationやGorguts、Today Is The Dayらの影響を消化し独自の個性を確立した作編曲は壮大な交響曲のようであり(インタビューによれば、よく比較されるDeathspell Omegaからの影響はないとのこと)、現代ジャズ方面の語法を取り込みテクニカルデスメタルの形式を発展させた演奏は超絶技巧を無駄打ちしない必然性に満ちている。本作はバンドの音楽性が最初の完成をみせた2ndフルで、以降の傑作群と並べても見劣りしない(今なお最高作の一つとされる)充実の内容になっている。作品を発表するたびに影響力が増す現代最強バンドの一つである。
Deathspell Omega:Paracletus(2010)

Deathspell Omegaはブラックメタルの領域における歴史的名バンドであり、日本では2004年の『Si Monvmentvm Reqvires, Circvumspice』(ハイライトとなる大曲で滝廉太郎「荒城の月」の荘厳な合唱が入る)が大きな話題を呼んだことからそのあたりのイメージを引きずっている人も多い。しかし、続く2005年の『kenose』でそれまでの定型的ブラックメタル寄り音進行(19世紀クラシック音楽に通じる素直な展開が主)に不穏な響きを加え始めたあたりから路線転換がなされていき、2010年発表の本作『Paracletus』では上記の4バンドと並べても違和感のない“不協和音デスメタル”的なスタイルが確立された。ライヴもインタビューも殆ど行わない覆面バンドなので音楽的バックグラウンドも謎な部分が多いのだが、ConvergeやThe Dillinger Escape Planをはじめとするカオティックハードコア(これは日本での通称で英語圏では一般にMetalcoreとかMathcoreといわれる)とデスメタルの間にあるような独特の質感や曲展開もあわせ、独自の非常に優れた音楽性を築き上げている。メンバー(と目されている人物)にはネオナチ疑惑があり、シーン内での批判も多く手放しで持ち上げることはできないのだが、作品の魅力や実際に及ぼしてきた影響の大きさを否定することは難しい。好んで聴くかどうかはともかく非常に重要な役割を担ってきたことは認めざるを得ないし、不協和音デスメタル的な音楽性の作品を語る際に比較対象として挙げられることが非常に多い(そしてそれは誤っていることも多い)バンドでもある。
DsOの影響力についてはこちらの記事が参考になる:
DIES IRAE:Deathspell Omegaに似てるバンド・アルバム集 (livedoor.jp)
Gorguts:Colored Sands(2013)

2005年に一度活動停止、体制を刷新した上での復活作。2010年代以降のこのシーンにおける歴史的名盤である。交響曲的な作編曲の強度は『Obscura』および次作『From Wisdom to Hate』より数段上、演奏と音響の練度も驚異的(2014年7月の来日公演でも信じられないくらい素晴らしい出音&PAを聴かせてくれた)。それに加えて重要なのがメンバーの人脈で、現在も在籍するColin Marston(KralliceやDysrhythmiaなど多数)とKevin Hufnagel(DysrhythmiaやVauraなど)、2014年に脱退するJohn Longstreth(Hate Eternal, Origin)、そして絶対的リーダーLuc Lemayという布陣は、初期デスメタルからブルータルデスメタルを経由しNYの越境的アンダーグラウンドメタルに繋がる歴史を総覧し接続するものでもある。現代の“不協和音デスメタル”を象徴する最重要アルバム。
Portal:Vexovoid(2013)

Portalはメタルという形式の上での抽象表現を突き詰めたようなバンドである。出発点は確かにImmolationやIncantationのような“リチュアル系”荘厳儀式デスメタルなのだが、作品を重ねるほどに唯一無二の境地を拓き続け、似たようなスタイルを選ぶことはできるが同じ味は出せないというポジションを確立してきた。慣れないと音程を聴き取るのも難しい暗黒音響もさることながら、最も個性的なところは「どうしてそんな展開をするのか何度聴いてもよくわからない」曲構成だろう。コード感的にはGorguts系の無調的なものではなく、19世紀末クラシック音楽あたりの比較的わかりやすい響きが主なのだが、フレーズの並びというか起承転結の作り方が不可解で、ある種のドラマ(およびその傾向)は確かに存在するのだが一体どこに連れていかれるのかわからない印象が付きまとう。そう考えると、例えばラヴクラフト的な荘厳&理不尽の表現(顔の見えないローブをまとう儀式的なライヴパフォーマンスもそれに通じる)としては至適なものに思え、コネクトしやすい部分も備えつつ総合的には全く手に負えないというこの按配こそが肝なのではないかという(くらいのところに留まらざるを得ない)納得感が得られる。本作は代表作として挙げられることが多い4thフルで、スタイルというか表現の方向性自体は2003年の1stフルの時点で概ね固まってはいる。どれを聴いても似たような具合によくわからない、しかし各々で描かれる気分や情景は確かに異なっている、という積み重ねも凄まじい。大きな影響力を発揮しつつ余人の追随を許さない重要バンドである。
Blood Incantation『Starspawn』(2016)
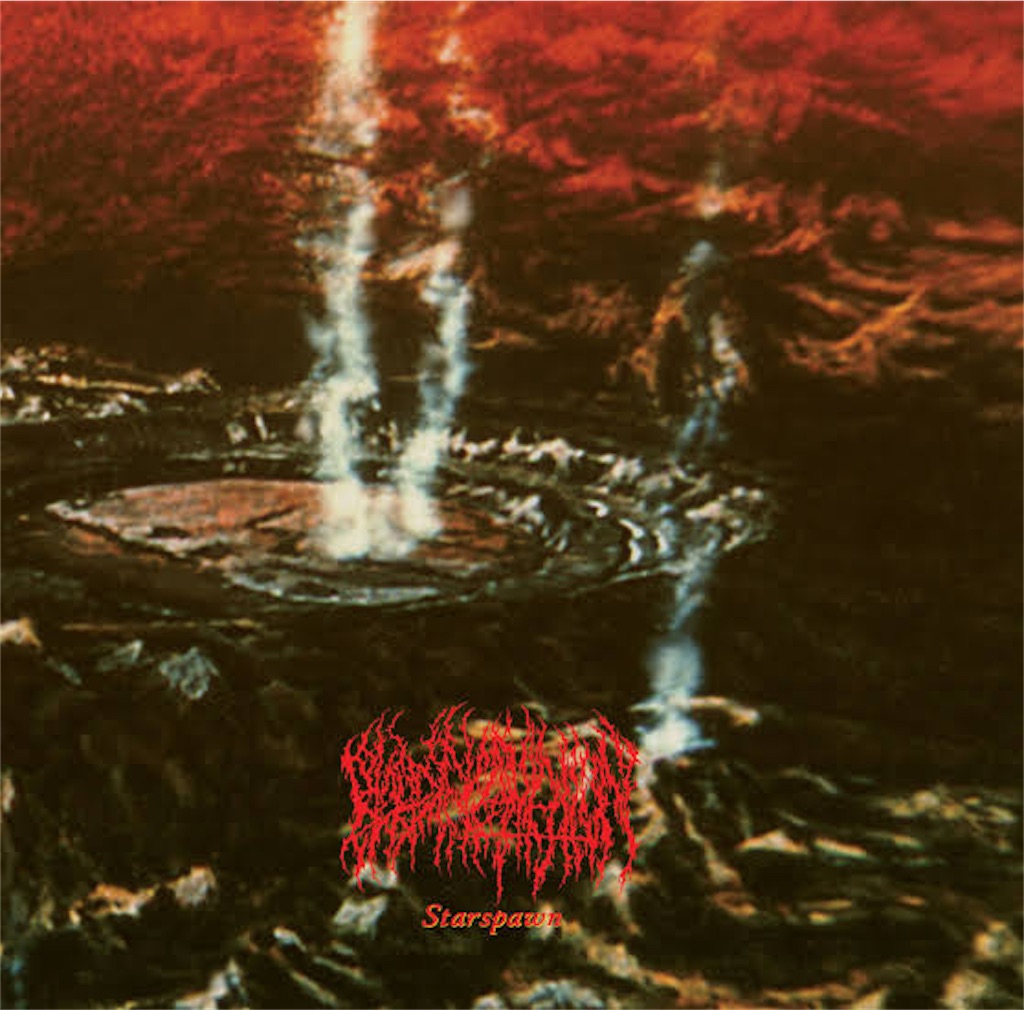
Blood Incantationは昨今の初期デスメタル(Old School Death Metal=OSDM)リバイバルにおける代表的なバンドである。1stフルである本作はTimeghoulとImmolationの美味しい所をMorbid Angel経由で混ぜ合わせたような音楽性で、不協和音をキャッチーに聴かせる作編曲の良さや、生々しいヨレや揺らぎを魅力的に聴かせる演奏および録音など、OSDMのエッセンス(特にコズミックデスメタル)を現代的に料理する巧みな仕事により2016年を代表するデスメタルアルバムとして多方面から高い評価を得た。このバンドはメンバーの兼任バンドも非常に重要で、diSEMBOWELMENT路線の昇華が見事なSpectral Voice、フィンランド型デスメタルの再構築が素晴らしいBlack Curseなど、シーン最重要バンドの多くが数珠つなぎ状に連関している(その2つのバンドの要素も本作に含まれ豊かさを増している)。
2019年の2ndフルは中期DeathやMorbid Angelの要素を増しつつDemilichオマージュ(同バンドのリーダーAntti Bomanがゲスト参加)をするなど、ここ数年のOSDMリバイバルをある意味総括する内容になったが、PitchforkのBest New Music(その週の最高評価)として8.3点を獲得、年間ベストでも41位(メタルは本作のみ)にランクインしたりと、ジャンル外からも熱い注目を浴びることとなった。その理由はよくわからないのだが(1stフルの高評価を受けて「この作品を押さえておけば専門外ジャンルの地下シーンも分かってることが示せてセンス良く見える」的な枠に入れられた感もある)、それに見合った内容や文脈的価値を備えた作品ではある。こうした面においても非常に重要なバンドである。
Pyrrhon:What Passes for Survival(2017)

Pyrrhonは作品のクオリティ的にも人脈的にも“不協和音デスメタル”の先端部を代表するバンドである。Gorgutsにヘヴィ・ジャンク的な質感やグラインドコア流フリーミュージック的な展開(即興から構築されるアンサンブルも含まれる)を加えフォーク~アメリカーナ的な仄暗い豊穣に潜っていくような音楽性は、Swansに代表されるニューヨークならではの文化の坩堝的特質を継承するものだし、Today Is The Dayの混沌を損なわずデスメタル形式に完璧に落とし込んだような趣もある。SeputusやImperial Triumphantといった強力なバンドとの人脈的接続(または重複)も重要で、現代ジャズなどジャンル外の様々な領域に繋がる窓口にもなっている。このシーンの結節点・羅針盤としても外せないバンドである。
Krallice:Mass Cathexis(2020)

Kralliceは初期の“ポストブラックメタル”的な音楽性で知られるが、一時期以降はそこを脱し、地下メタルのエッセンスを巧みに掛け合わせ新たなものを生み出す活動を続けてきた。本作はその集大成とも言える傑作で、TimeghoulやNocturnusが土台を築き上げBlood Incantationが昇華させたことにより脚光を浴びるようになったコズミックデスメタル、EmperorやLimbonic Artに連なる宇宙的なシンフォニックブラックメタル、Ved Buens Ende...や一時期以降のDodheimsgardに連なる現代音楽~フリージャズ寄りのアヴァンギャルドブラックメタル、Gorgutsの系譜にある不協和音デスメタル、そしてそれら全てに大きな影響を与えたVoivodなど、様々なスタイルおよび文脈がこのバンドにしか成し得ない形で魅力的に統合されている。Colin Marston(Gorgutsのメンバーであり、近年のテクニカル系デスメタル作品の多くに関与する名エンジニアでもある)をはじめとしたメンバーの膨大な関連プロジェクトも鑑みれば、Kralliceは音楽的達成の面においても人脈の面においても現代メタル最重要グループの一つと言っても過言ではない。このシーンを掘り下げる際は必ず注目しなければならないバンドである。
【ルーツ】背景理解を助けてくれる20枚
Swans:Filth(1983)

ヘヴィな音楽の歴史において最も重要なバンドの一つ。ポストパンク~ノーウェーヴの無調的コード感をさらに推し進めた音進行(または反復)感覚、グラインドコアに繋がる重苦しいジャンク音響、それらに表現上の必然性を与える殺伐とした雰囲気など、同時代以降の音楽に与えた衝撃は測り知れないものがあるし、“不協和音デスメタル”周辺のバンドも間接的または直接的に大きな影響を受けている。ニューヨークの越境的な地下シーンを紐解くにあたっても外せない存在である。
G.I.S.M.:DETESTation(1983)

G.I.S.M.は元祖メロディック・デスメタルと言われるくらい流麗な旋律を前面に押し出した音楽性で知られるが、クラシック音楽や歌謡曲に通じるリードフレーズに対しそれを包むコード感はかなり特異で、伝統的ハードロック~ヘヴィメタルやそれに連なるメロデスよりも、和声構造の複雑なデスメタルやSwansなどに通じるところが多い。これはインダストリアル~ノイズからの影響を解きほぐし巧みにまとめ上げたことにより生まれたと思われるもので、それを初期パンク~ハードコア的な流儀のもとで提示するG.I.S.M.の音楽は、様々なヘヴィミュージックが変遷混淆し新たなスタイルを生み出していった80年代初頭における、そうしたもの全てにとっての結節点なのだと言える。世界的に神格化されているだけのことはある(Meshuggahのようなバンドも影響を受けている)歴史的名盤。
Metallica:Master of Puppets(1986)

本作はスラッシュメタルの代表的名盤として語られることが多いが、メタルの歴史においては交響曲的な作編曲(曲単位でもアルバム単位でも)を確立した記念碑的傑作とみる方がしっくりくる。あまり注目されないけれども重要なのが「The Thing That Should Not Be」で(MeshuggahのMarten Hagstromはこれを「生まれ変わったら書いてみたいこの1曲」に挙げている)、Morbid Angelなどに直接的に通じるコード感覚は“不協和音デスメタル”の系譜にも非常に大きな影響を与えていると思われる(それとラヴクラフト的な歌詞テーマの組み合わせも)。史上最高のメタルアルバムの一つである。
Voivod:Killing Technology(1987)

“不協和音メタル”という括りを考える際に真っ先に名前が挙がるバンドがVoivodだろう。King Crimsonをはじめとしたプログレッシヴロックの音進行をNWOBHM的なパワーコード感覚で肉付けした音遣いは蠱惑的な魅力に満ちており、7拍子や5拍子を効果的に使いこなすリズム構成もあわせ、本稿に挙げたバンドのほぼ全てが直接的または間接的な影響下にある。本作は独自の大曲志向が最初に確立された傑作で、宇宙的な広がりと土着的な荒々しさを両立する独特の世界観~雰囲気表現は、“Sci-Fiメタル”“コズミックデスメタル”と呼ばれるスタイルの雛型となった。アンダーグラウンドなメタルおよびハードコアの歴史において最も重要なバンドの一つである。
Watchtower:Control And Resistance(1989)

テクニカルなメタルの世界における金字塔的傑作。Rushに連なるプログレッシヴハードロックの変拍子構成を高速スラッシュメタルに落とし込み、フュージョン(というかジョン・コルトレーン~マイケル・ブレッカーの系譜)をより複雑にしたようなコード進行と掛け合わせた音楽性で、Dream Theaterを含む同時代以降のバンドに絶大な影響を与えた。特に素晴らしいのが圧倒的な演奏表現力で、超絶技巧をひけらかし感なく必要十分に使いこなすアンサンブルは、どんな場面でも理屈抜きの生理的快感に満ちている。いわゆるマスコアとは異なるめまぐるしいビートチェンジ(13拍子や44拍子なども滑らかに駆使)はプログレッシヴデスメタルやテクニカルデスメタルの礎となり、その上で超えられない頂点として君臨し続けている。本稿に挙げた全作品の中で最も優れたアルバムの一つである。
詳しくはこちら
Toxik:Think This(1989)

スラッシュメタルというよりはスピードメタル(NWOBHMを高速化したもので音進行の傾向が異なる)の系譜にあるバンドなのだが、この2ndフルではMahavishnu Orchestra経由でストラヴィンスキーに接続するような入り組んだ音楽性に変化。複雑な構造を極上のリードギター(エディ・ヴァン・ヘイレンやウリ・ジョン・ロートをさらに流麗にした感じ)で彩る作編曲が圧巻で、何度聴いても汲み尽くしきれない妙味に満ちている。メタルの歴史全体を見渡してもトップクラスの実力があるのに一般的にはほとんど無名なのが残念。影響関係を云々するのも難しいオーパーツ的傑作である。
Morbid Angel:Altars of Madness(1989)

Morbid Angelはデスメタルの世界に最初に複雑なコード感覚を持ち込んだバンドの一つである。19世紀末~20世紀初頭のクラシック音楽(無調になる前あたり)の暗黒浮遊感あふれるコード感をラヴクラフト的な世界観と併せて魅力的に聴かせる作編曲が圧倒的に素晴らしく、ジャンルの立ち上げに関わった古参でありながら今も最強の一角として君臨し続けている。“不協和音デスメタル”の系譜で重要なのは中期の傑作『F』『G』(このバンドのアルバム名はアルファベット順に考案されている)あたりだが、一枚選ぶならやはり『A』だろう。最初期ならではの衝動的な勢いが既に卓越した演奏技術と絶妙に融合し、作編曲もまだ抽象的になりすぎず程よいキャッチーさに満ちている。個人的には“デスメタル”に括られるあらゆる作品の中で最も好きなアルバムの一つ。永遠の名盤である。
Carcass:Symphonies of Sickness(1989)

初期のCarcassはゴアグラインドの始祖として語られることが多いが、独特の暗黒浮遊感を伴う特殊なコード感覚の面でも後のエクストリームメタル全域に絶大な影響を与えている。この2ndフルは低域に密集した轟音が整理され構造の細部を見通しやすくなってきた時期の作品で、それに対応するかのように曲構成も長尺・複雑化。慣れないと音程を聴き取るのも一苦労だが、ひとたび耳が馴染めば最高級の珍味に没入することができる。グラインドコアや北欧のデスメタルを通過した音楽は多かれ少なかれCarcass的な音進行傾向を血肉化しているし、“不協和音デスメタル”の系譜を読み込むにあたっても無視できない重要なバンドだと思われる。
詳しくはこちら
Pestilence:Consuming Impulse(1989)

Pestilenceは初期デスメタルからプログレッシヴデスメタルが立ち上がっていく流れを象徴するバンドである。スラッシュメタルの速さを損なわず重く安定させたような最初期の作風に次第に特異なコード感が加わっていき、1994年の解散前から2008年の再結成以降にかけては独自の音進行感覚を完全に確立。他の何かと比較するのが無意味に思われるほど個性的な(初聴では良し悪しを評価するのも難しい)路線を開拓し続けている。本作2ndフルはデスメタルの一般的なスタイルにまだ留まっていた時期に発表した歴史的名盤で、Morbid Angelを少しジャズに寄せたような和声感覚はいわゆるプログレッシヴデスメタルにおける重要な雛型となった。聴きやすさも鑑みれば総合的にはキャリア最高作と言っていいだろう一枚。簡潔的確なプレゼンテーションの大事さを実感させてくれる傑作である。
Obliveon:From This Day Forward(1990)

本稿に挙げたバンドは一般的にはほぼ無名ではあるものの一定の文脈では極めて高く評価されているものも多いのだが、Obliveonはそうした領域でさえ実力や功績に見合った認知を得ていない不遇の存在である。VoivodやGorguts、Martyrなどを生んだカナダ(特にケベック)のシーンでも屈指の実力者で、作品のクオリティはそれらの傑作群にも勝るとも劣らない。本作1stは最もスラッシュメタル色の強い1枚であり、同郷の伝説的クロスオーバーハードコアバンドDBCをDestructionのような欧州スラッシュメタルに寄せた趣の傑作になっている。Voivodの音進行感覚を数段洗練し暗黒浮遊感を増したような作編曲は唯一無二の個性に満ちており、2000年代に入ってからVektorやNegative Planeといったバンド群がリバイバル的に立ち上げた“Sci-Fiメタル”“コズミックデスメタル”の潮流をより高い完成度で先取りしている感もある。それに加えて重要なのが音楽制作スタッフとしての役割で、ギターのPierre Remillardはエンジニアとしてカナダ周辺バンドの傑作の多くに関与(Cryptopsy、Gorguts、Martyr、Voivodなど)。裏方として大きな信頼と影響力を得ていることが窺える。発表した作品は全て廃盤、各種ストリーミングサービスはおろかBandcampにすら音源が上がっていない現状をみると、十分に知られるのはまだまだ先になりそうなのだが、“テクニカルスラッシュメタル”から“プログレッシヴデスメタル”を経由し“不協和音デスメタル”にも深く関与(Gorgutsの最重要2作にもエンジニアとして参加)するこのバンドが見過ごされたままでいいわけがない。注目される機会を得て適切に評価されてほしいものである。
詳しくはこちら
Atheist:Unquestionable Presence(1991)
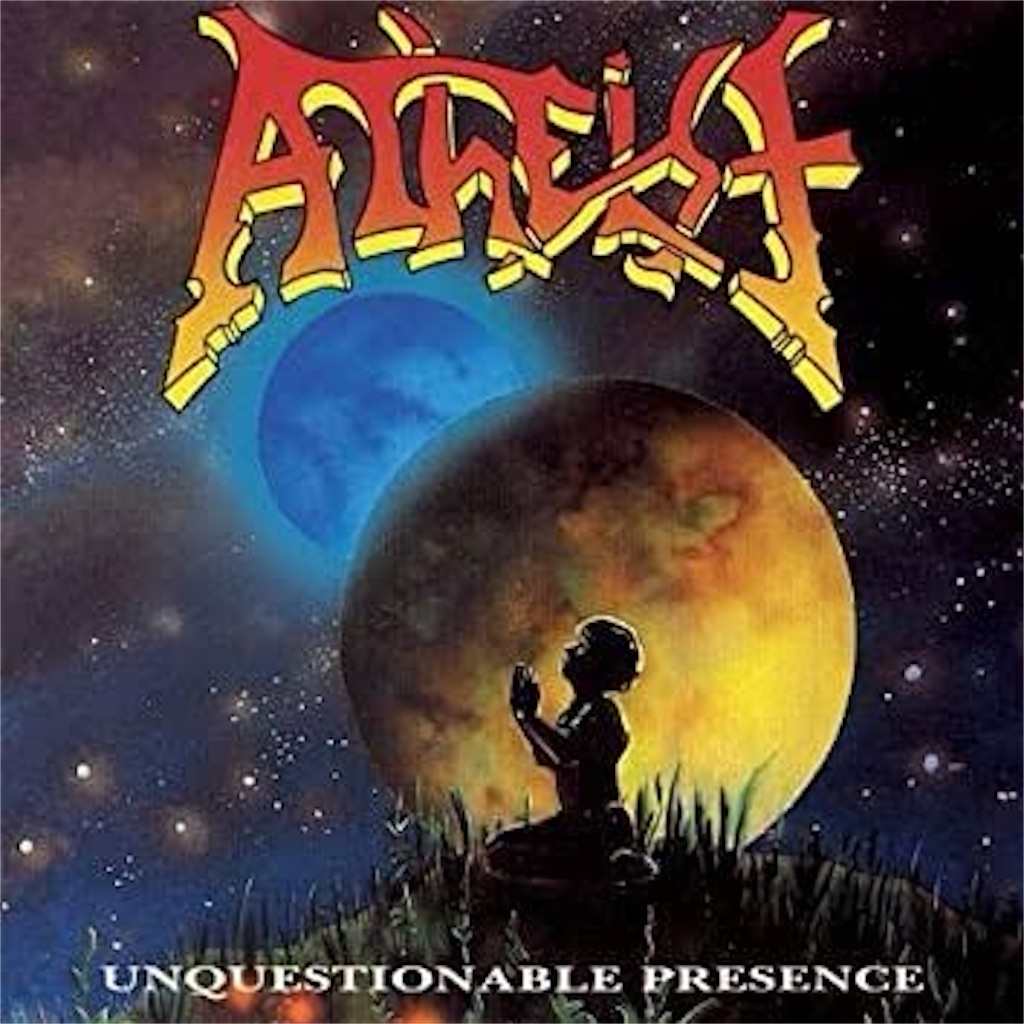
AtheistはDeathやCynicと並ぶ“プログレッシヴデスメタル”黎明期の伝説的名バンドとして挙げられることが多いが、確かに初期デスメタルシーンに所属してはいたもののそれらとはだいぶ毛色が異なるし、現在“プログデス”として認識されるスタイルと直接的には繋がらない音楽性を確立していた。1stフル『Piece of Time』(1989)再発盤のライナーノーツでリーダーのKelly Shaeferが述べているように、成り立ちの基本は「Rush+Slayer+Mercyful Fate」という感じで、そこに様々な音楽要素を溶かし込みながらも形式面では大きく離れない出音は「モードジャズ化したNWOBHM寄りスラッシュメタルを超一流のジャズロックプレイヤーが演奏している」ような趣がある。フュージョンやクラシック音楽~現代音楽に学びコード進行的な考え方から楽曲を構築する多くの“不協和音デスメタル”とは異なり、Atheistは転調(広く定着した誤用としてのビートチェンジではなく、tonal centerを変更するキーチェンジ)を繰り返す単旋律リフの積み重ねによって複雑な表情を描く傾向があり、それを支える感覚が特殊で唯一無二のものだということもあってか、同様の味わいをそのまま継承しているものは殆ど見当たらない。それは圧倒的なアンサンブルについても同様で、全パートがシーン屈指の超絶技巧を駆使して命を削るような演奏表現を繰り返すさまは、音楽史における一つの頂点をなしていると言っても過言ではない(特にSteve Flynnの神憑かったドラムスは誰にも真似できない)。以上のようなことを鑑みると、このジャンルの流れを語るにあたっては実は必要でないようにも思われるのだが、80年代までの伝統的なHard Rock / Heavy Metalがスラッシュメタルを経由して90年代以降のエクストリームメタルに繋がる系譜を体現する存在としては極めて重要だし、そこに留まらずメタル史上屈指の成果と言える作品群は広く聴かれるべき価値がある。“プログデス”云々のイメージを越えて高く評価されてほしいバンドである。
詳しくはこちら
Death:Human(1991)

デスメタルというジャンル全体を代表する名バンドDeathには二つの側面がある。一つは88年2ndフルまでの“初期デスメタル”路線、そしてもう一つは本作4thフル以降の“テクニカルデスメタル”“プログレッシヴデスメタル”路線である。1990年の3rdフルからチャック・シュルディナーのワンマンバンドとなったDeathは作品ごとにメンバーを入れ替えるようになり、本作では界隈を代表する超絶技巧ベーシストであるスティーヴ・ディジョルジオとCynicの2名(ギターのポール・マスヴィダル、ドラムスのショーン・レイナート)を招集。このジャンル全体をみても最も豪華な座組が出来上がることとなった。その3名も深く関与した作編曲は全編素晴らしく、繊細なニュアンスと膨大な手数を美しく両立するレイナートのドラムス(Cryptopsyのフロ・モーニエなど多くの達人を魅了した)をはじめとする歴史的名演もあわせ、後続に絶大な影響を与えている。シュルディナーは独特の和声感覚を持ってはいるもののコード弾きなどのアレンジでそれを具体的に掘り下げることはできなかった(Deathの楽曲は大部分が単旋律のリフから構築されている:その意味において“不協和音デスメタル”に括るのは不適切にも思われる)のだが、本作ではマスヴィダルの貢献もあってか、単旋律主体アレンジからくるモノトーン感とそこから醸し出されるコード感が絶妙なバランスで両立されている。ジャンルの確立を告げる(オリジネーターとしてではなく編集者的な意味での)記念碑的傑作である。
Deathの項に関連して述べておきたいのが、本作を起点とした“プログレッシヴデスメタル”の語られ方の歪さである。この領域のファンはいわゆるプログメタル(Dream Theaterなどの系譜)を好む一方で初期デスメタルは殆ど聴いていないタイプの人も多く、新しいバンドの音楽性や影響関係を云々する際、Death(本作4th以降のみ)やCynic、AtheistやGorgutsといった“プログレッシヴデスメタル”枠の名前を挙げて良しとすることが非常に多い。しかし、例えばBlood IncantationはDeathはともかくCynicやGorgutsと比較するのは不適切、較べるならImmolationやTimeghoulの方が遥かにしっくりくるし、GorgutsのリーダーLuc Lemayが「Deathの『Scream Bloody Gore』(1987年1stフル)を聴いたとき人生が変わった」と言っていることも鑑みれば、“プログレッシヴデスメタル”以外の(綺麗に整ってはいない)デスメタルも参照しなければ適切な理解を深めることができないのは明らかである。その“プログレッシヴデスメタル”とは異なる文脈も多い“不協和音デスメタル”ではその傾向は一層強くなるだろうし、活発に新陳代謝を繰り返すシーンの実情とその認知状況との乖離をこれ以上拡大させないようにするためには、こうしたルーツの把握も踏まえた批評の更新が必要になる。本稿がその一助になれば幸いである。
Disharmonic Orchestra:Not to Be Undimensional Conscious(1992)

Disharmonic Orchestraはオーストリア出身のトリオバンドで、グラインドコアと初期デスメタルが不可分に接続しながら立ち上がっていくシーンの黎明期(1987年)に結成された。ギター+ベース+ドラムス+ボーカル(音程変化のない歪み声)の最小編成でOrchestraを名乗るのはどうなのかと思われるかもしれないが、このバンドはその名のとおりの素晴らしい不協和音アンサンブル構築に成功している。Napalm DeathやCarcassの系譜にある変則的なコード遣いにゴシックロック的なアウト感覚を加えた音進行は蠱惑的な魅力に満ちており、異常にうまい演奏(渋くまとまっているがAtheistやCynicに勝るとも劣らない)もあわせ代替不可能な滋味を確立。「The Return of the Living Beat」後半におけるスクラッチ+ラップの導入(90年代頭のメタルシーンでは嫌われた試み)なども全く違和感なくこなす本作の楽曲はいずれも名曲級であり、このジャンルで最も優れたアルバムの一つとさえ言える。しかしバンドはそれに見合った注目を得ることができず、今に至るまで一般的な知名度はゼロに近いまま。90年代前半のデスメタル周辺シーンにはこうしたオーパーツ的傑作が多く、マニア的な探究をする者にとっては金脈のようでとても楽しいのだが、正当な評価がなされるべきという観点からすればやはり好ましくないし、そういう状況におかれても傑作を発表し続けているこのバンドの活動も多少はやりやすくなるようサポートできたのではないかと思ってしまう。The Dillinger Escape Planのメンバーが愛聴するなどシーン内での影響力も少なくないだろうし、もう少し注目されていいバンドなのではないかと思う。
Cynic:Focus(1993)

“プログレッシヴデスメタル”の頂点として君臨し続ける永遠の名盤。メンバーはジャズやプログレッシヴロックなどメタル外からの影響の方が大きく、そうした超絶技巧や楽理を活かす場としてのエクストリームメタルという意義が理想的な形で具現化されている。参照元と思われるYesやアラン・ホールズワース、世界各地の民俗音楽やアンビエントなどに通じるパーツはあるものの、全体としては完全に別物で、溶けかかった金属のスープが蠢くような不思議なグルーヴは似たものが見当たらない。デスメタルに明確な歌メロやオートチューンを導入し美しく活かすなど、本作が切り拓いた可能性は枚挙に暇がなく、その存在感はKing Crimsonの1stフルにも比肩する。作編曲も演奏も最高レベル。究極のロックアルバムの一つである。
Demilich:Nespithe(1993)

1990-1993年の本活動時は完全に無名で、マニアの間でのみカルトな名盤として語り継がれてきた本作も、ここ数年のOSDMリバイバルを経たことで史上最も重要なデスメタルアルバムの一つとみなされるようになってきた感がある。自分はAmazonレビューで本作を知り、ディスクユニオン御茶ノ水店でたまたま見つけて買ったことからその圧倒的な個性と完成度に惹き込まれるようになったわけだが、20周年記念盤掲載のAntti Boman(バンドの絶対的リーダー)インタビューなどを参考にこの記事をまとめた2015年の時点ではここまで再評価の気運が盛り上がるとは想像することもできなかった。しかし、Chthe'ilistやTomb Moldのような現行シーンの超一流バンドがDemilichのエッセンスを土台に各々の個性を開花させることによって知名度は着実に増していき、Blood Incantationの2019年2ndフルでAntti Bomanがゲストボーカルとしてフィーチャーされたことでその名声は決定的になったといえる。
本作がここまで注目されるようになったのは、アルバム全体の完成度が極めて高い(曲順構成や雰囲気的な統一感は完璧)というのもあるだろうが、素材としてそこに様々なものを付け加えやすい音楽性だからというのが最大の理由なのではないかと思われる。単旋律のリフを並べてモノトーンな広がりを生んでいく構成はAtheistやDeathにも通じるが(瞬間的に転調を繰り返しつつ足場は揺るがない感じの進行はその2者とはタイプが異なる)、そこに肉付けするコードの質によって様々に異なる表情を描くことができる“素材としての自由度”に関してはDemilichの方が格段に上で、パーツを拝借してもアレンジ次第で独自の個性へ昇華しやすい。上に名前を挙げたChthe'ilist・Tomb Mold・Blood Incantationも(他に溶けている要素が多くそれぞれ異なるからでもあるが)全く別のオリジナリティを確立しているし、そうしたシンプルで奥深い持ち味、いうなれば“異界の鰹節”的な特性が卓越しているからこそ、時を越えてここまで大きな流れを生むことができたのだろう。その上で、その特性を単体で提示する本作の抽象的表現力も後続と同等以上に素晴らしい。現行シーンの作品と併せて聴くことで双方の理解が深まる稀有の傑作である。
diSEMBOWELMENT:Transcendence into the Peripheral(1993)
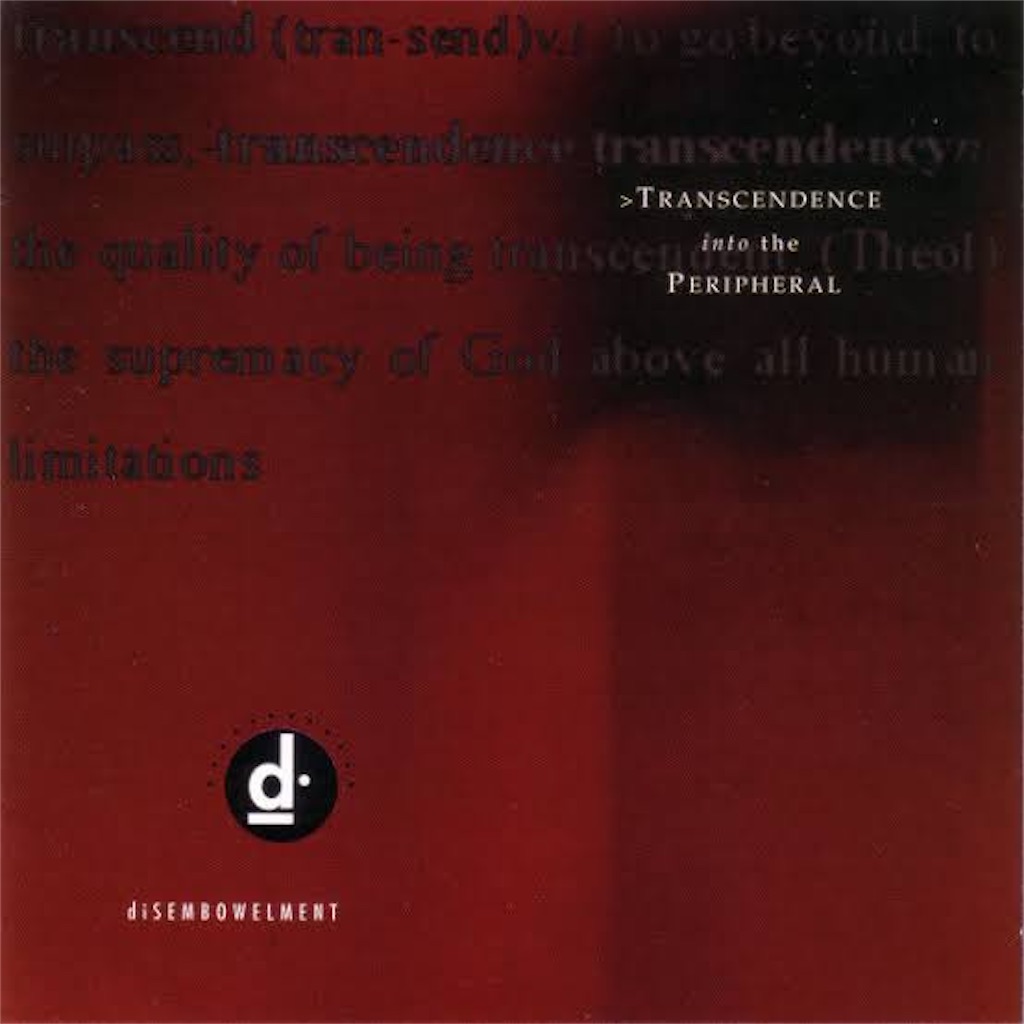
デスメタルという音楽の可能性を最も体現する究極のアルバムの一つ。The CureやJoy DivisionからDead Can Danceあたりに連なるゴシックロックと初期Napalm Deathのようなグラインドコアの暗黒浮遊感を足し合わせ、中東音楽~ビザンティン音楽~古楽を経由してアンビエントに接続したような音楽性で、フューネラルドゥームと呼ばれるジャンルの一つの雛型にもなった。7曲60分の長さを難なく聴き通させる構成力は圧巻で、アルバム全体を覆う厳粛な雰囲気や固有の時間感覚もあわせ、他では得られない特別な音楽体験を提供してくれる。これもDemilichと同じく知る人ぞ知るカルト名盤だったのだが、Blood Incantationの兼任バンドSpectral Voice(4人中3人が共通)がオマージュを捧げたこともあって知られる機会が増えてきている。現行デスメタルシーンを理解する資料としての重要度も年々高まっていくだろうし、作品それ自体の内容もこの上なく素晴らしい。未聴の方はこの機会にぜひ聴いておかれることをお勧めする。
詳しくはこちら
Timeghoul:Panaramic Twilight(1994)

Timeghoulは、近年熱い注目を浴びる“コズミックデスメタル”の始祖としてカルトな信奉を集めるバンドである。前身のDoom`s Lyre(1987-1991)を含め1994年の解散までに発表した作品は2つのデモ音源のみで、流通の問題もあって知る人ぞ知る存在に留まる期間が長かったのだが、その2作をまとめた音源集『1992-1994 Discography』が2012年に再発されてから一気に認知度が高まり、Blood Incantationをはじめとした現代デスメタルの代表的バンドがスタイルを援用したこともあわせ、重要バンドとしての地位がほぼ固まった感がある。この系統の先駆者としてよく知られるNocturnus(初期Morbid Angelと人脈的な繋がりがあり注目されやすかった)よりも高く評価されるようになってきた理由としては、Timeghoulの方が圧倒的に曲が良いのが大きいだろう。Nocturnusは「デスメタルにシンセサイザーやSFテーマの歌詞を最も早く導入したバンドの一つ」と言われるとおり音遣いや世界観の表現は面白いのだが、リフや曲展開は比較的凡庸で、固有の味はあるものの突き抜けた説得力には欠けるという難があった。それに対しTimeghoulは全ての要素が強力で、ショスタコーヴィチやストラヴィンスキーとも比較される刺激的な作編曲は、Gorguts『Obscura』以降の“不協和音デスメタル”とそのまま並べてしまえるものになっている。2ndデモである本作は音質の良さもあってそうした魅力がわかりやすく提示されている傑作で、『Obscura』の項でふれた「実は1993年には殆ど完成しており、1998年の発表当時ですら時代の数歩先を行っていたこのアルバムが順調にリリースされていたら音楽の歴史はどんなふうに変わったのだろうか」という仮定の話を実現したかのような存在感がある(こちらも発表当時は十分な知名度を得ることはできなかったのだが)。“コズミックデスメタル”についてどうこう言う際には絶対に聴いておかなければならないバンドである。
Meshuggah:Destroy Erase Improve(1995)

Meshuggahはメタルのリズム・和声・音響に革命を起こした最重要バンドである。パーツは変拍子だがフレーズ全体では4拍子に収まり4~8~16小節を1周期とする拍構造(その意味で「ポリリズム」は誤り)、アラン・ホールズワースなどの無調的コード遣いを発展させた高度な音進行、そうした複雑な構造が分からなくても楽しめる重く切れ味の良い音作り。こうした音楽性はDjent(ジェント)という直系ジャンルを生み大流行させたほか、現代ジャズなど他領域にも絶大な影響を与えている。デスメタルの文脈で語ることはできないが、Car Bombをはじめ“不協和音デスメタル”周辺のバンドに及ぼした影響も大きく、併せて聴き込む価値は高い。本作は以上の要素が未洗練ながら魅力的に確立された一枚で(13拍子などの変拍子も残存)、過渡期だからこその豊かさと驚異的な完成度を両立。90年代北欧ならではの薫り高い雰囲気も絶品な名盤である。
Ved Buens Ende...:Written in Waters(1995)

いわゆる“アヴァンギャルドブラックメタル”を代表するバンド。唯一のフルアルバムである本作は、ノルウェー以降のブラックメタルシーン(たまたまメタルを主題としているだけで音楽的には何でもありの豊かな領域)が生み出した最高の達成の一つというだけでなく、90年代のあらゆる音楽ジャンルをみても屈指の傑作である。音楽性を一言で表すのは困難で、基本軸を示す饒舌なベースの上でギターが無調寄りの複雑なコード付けを繰り返し、それらを卓越したドラムスがじっくり彩る、というアンサンブルは「現代音楽に通じるフリー寄りモードジャズ(エリック・ドルフィーあたり)をAmebixと組み合わせてブラックメタル化したもの」とか「King Crimson~Voivodとノルウェー特有の音進行感覚を混ぜ合わせて独自の暗黒浮遊感を生み出したもの」というふうに言うことはできるが、作編曲や演奏表現の底知れない豊かさはそうやって形容できるレベルを遥かに超えている。“アヴァンギャルドブラックメタル”という括りで認識されるスタイルはここで練り上げられた不協和音感覚を発展させたものが多く、メンバーのVicotnikが結成したDodheimsgardやCarl-Michael Eideが率いていたVirusなどはその代表格として未踏の境地を切り拓き続けてきた。現行の “不協和音デスメタル”周辺でもこうした“アヴァンギャルドブラックメタル”的な要素を駆使するバンドが存在することを鑑みれば、Ved Buens Ende...関連の音楽を聴いておくことはシーンの理解に少なからず役立つのではないかと思われる。
なお、こちらの記事では2007年に再解散したと書いたが、Ved Buens Ende...は2019年に再々結成し、オリジナルの3人+サポートドラマーの編成で今も活動を続けている。メンバーはいずれも驚異的な傑作を作り続けてきた才人だし、この名義でも新たなアルバムを生み出してくれることを願うばかりである。
The Dillinger Escape Plan:Calculating Infinity(1999)

いわゆるカオティックハードコアを代表するバンド(これは日本での通称で英語圏では一般にMetalcoreとかMathcoreといわれる)。この1stフルはジャンルのイメージを決定付けた歴史的名盤で、King CrimsonやMahavishnu Orchestraといったプログレッシヴロック~ジャズロック、CynicやMeshuggahのような“プログレッシヴデスメタル”周辺、DeadguyやDazzling Killmenに代表されるメタリックなハードコア、DeathやToday Is The Dayのようなデスメタル周辺など様々な領域のエッセンスを咀嚼し、Aphex TwinやSquarepusher、AutechreなどのIDM(Intelligent Dance Music)を人力で再現できてしまう驚異的な演奏表現力をもって統合した結果、複雑な和声と変拍子が目まぐるしく切り替わるのに快適に聴き通せてしまう異常な音楽が生まれている。このバンドが何より素晴らしいのはこれほどの超絶技巧を備えているのにそれに全く溺れないところで、最後の来日公演でも十全に示されていたように、20年の活動期間の全編にわたって衝動を最優先する表現を続けてきた。こうした姿勢は“不協和音デスメタル”周辺にも大きな刺激を与えており、Car Bombのような重要バンドが参考にしたことを公言するだけでなく、Deathspell OmegaやEphel Duathなどを通してジャンル外(ハードコアそのものは好まないだろう領域)にも少なからず影響を及ぼしていると思われる。“不協和音デスメタル”はメタルの中でも特に高度な作編曲が求められる音楽スタイルであり、シンプルな構造と勢い一発で突っ走る演奏のイメージが強いだろうハードコアとはあまり結び付かない印象もあるかもしれないが、作編曲もアンサンブルも超絶的に高度なバンドはハードコア方面にも多数存在し、特に2000年代に入ってからはメタル方面全域に影響を与えている。TDEPはその嚆矢となる存在であり、今なお聴き込む価値の高い名盤を多数遺した重要バンドなのである。
【その他の重要作】現行シーンを俯瞰する20枚
Martyr:Feeding the Abscess(2006)

後期DeathやCynicを“プログレッシヴデスメタル”の第1世代とするならば、Martyrはそれらに直接影響を受けた第2世代の代表格であり、この系譜における史上最高のバンドの一つでもある。メンバー全員が音楽学校で正規の教育を受け、そこで得た楽理や技術を駆使しつつ衝動的な勢いや神秘的な深みの表現を追求。知識があるからこそ到達できる個性を確立した音楽性は第1世代の名作群の味を損なわず強化するもので、活動期間中に遺したフルアルバム3作とライヴアルバムはいずれもこのジャンルの歴史を代表する傑作といえる。本作3rdフルは最終作で、前作2nd(後期DeathやCynic直系の作品としてはこれ以上望めないレベルの内容)に較べると格段に入り組んだ展開を直情的に駆け抜ける音楽性は音響構築も含め完璧な仕上がり。Watchtower~Blotted Scienceを後期Emperor経由でバルトークあたりに接続し禍々しい怨念を注入したようなサウンドは、多くの定型的な“プログレッシヴデスメタル”が陥りがちなルーチンワーク的味気無さとは一線を画している。行きつくところまで行きついてしまったのでこれで解散、となるのもむべなるかなと思える驚異的な作品である。
上記のような作品自体のクオリティとは別に、Martyrはこのシーンにおける人脈的繋がりを象徴するバンドでもある。リーダーのDaniel MongrainはGorgutsの4th『From Wisdom to Hate』やCryptopsyの2004年ツアーにも参加したのち、不協和音メタルの始祖といえる名バンドVoivodに加入、絶対的リーダーだった先代Piggy(2005年に脳腫瘍のため逝去)に勝るとも劣らない素晴らしい仕事をし続けている(なお、Martyrの3rdフルにはVoivod「Brain Scan」のカバーが収録されている)。2018年発表のフルアルバム『The Wake』ではPiggyのリフ構築を換骨奪胎、個性を損なわずKing Crimson要素の呪縛から解き放つ手管が絶品だったし、2019年のモントリオール・ジャズ・フェスティヴァルでは『The Wake』収録曲をオーケストラとの共演編成にリアレンジ。ストラヴィンスキーとフランク・ザッパをVoivod(同曲はホルスト「火星」を意識してもいると思われる)経由で接続するような極上の達成をしている。これを収録したライヴEP『The End of Dormancy』で示されているようにオーケストラ抜き4人編成の演奏も圧巻で、2019年1月の来日公演でも本当に素晴らしいステージをみせてくれた。また、Martyrの2ndフルおよび3rdフルに参加したドラマーPatrice Hamelinは現在はGorgutsの正メンバーを務めているし、その2作にはエンジニアとしてObliveonのPierre Remillardが全面的に関与している。以上のように、Martyrはカナダ・ケベック周辺シーンの密接な関わりを示す結節点的な存在でもあり、自身の作品群の凄さも併せれば“不協和音デスメタル”関連における最重要バンドの一つと言っても過言ではない。2012年の解散には知名度面での苦戦も少なからず関係していただろうし、今からでも注目され正当な評価を得てほしいものである。
Car Bomb:Centralia(2006)

Car Bombの音楽性は一言でいえば「Meshuggah+The Dillinger Escape Plan」という感じで(これはメンバー自身が公言している)、そこにDeftonesやMy Bloody Valentine、Radiohead、Aphex TwinやAutechreなどを加えれば構成要素は一通り揃うとみてよさそうではある。その上で、出音はそれらから連想されるよりも数段複雑で、TDEPにスローパートを多数追加しつつ緩急の起伏(というか瞬発力表現の見せ場)を増やしたような展開構成は数回聴いた程度では楽曲の輪郭すら掴めない。こうした音楽性は一応マスコアに括られるものではあるが、Meshuggah~ジェントの系譜を通過した新世代の“プログレッシヴデスメタル”的な存在として(Car Bomb自体にデスメタルの要素は殆どないと思われるけれども)、“不協和音デスメタル”周辺のバンドにも大きな影響を与えている。本稿の冒頭で「初期デスメタルリバイバルやプログデスといった系譜で語るのが適当でない領域が拡大し続けているにもかかわらず、それを語る批評の観点や表現がいつまでも更新されずにいるのは好ましいことではなく、活発に新陳代謝を繰り返すシーンの実情とその認知状況との乖離がどんどん大きくなっていってしまう」と書いたが、その分水嶺となっているのがまさにCar Bombあたりの高度なハードコア出身バンドなのではないかと思われる。そうした点においても注目されるべき重要な存在である。
参考:
2019年4thフルの発表当時には長谷川白紙が感銘を受けた旨を話していたこともあり、エクストリームメタルとは別種の激しさを拡張し続ける現代ポップミュージックの文脈でも今後参照される機会が増えていく可能性はある。
Virus:The Black Flux(2008)

ノルウェー以降のブラックメタルシーンを代表する奇才の一人Carl-Michael Eide(通称Czral)が率いていたバンド。Carl-Michael自身が「Talking Heads+Voivodと呼ばれることが多い」というとおりのポストパンク寄りスタイルのもと、Ved Buens Ende...の複雑な和声感覚を洗練する形で掘り下げる活動を続けていた。「Virusは“avant-grade heavy rock”であり、ブラックメタルとは繋げて考えたくない(そもそも何かの一部として扱われたくない)。メタルファンにもオルタナファンにもアピールしうると考えている」というこのバンドの雰囲気表現は、アンドレイ・タルコフスキーやフェデリコ・フェリーニ、ピーター・グリーナウェイやデヴィッド・リンチ達の不穏な映画から大きな影響を受けているとのことで、Ved Buens Ende...の時点ではまだ無自覚・無意識レベルに留まっていた毒性を抽出し濃縮したという印象もある。社交的に洗練された殺人的ユーモア感覚を漂わせる音楽表現は“精製された呪詛”のような趣もあり、サウンド面ではボーカルも含め歪み要素は殆どないにもかかわらず非常に怖い。本作2ndフルはCarl-Michaelが2005年にビルの4階から転落しドラムス(メタル周辺の音楽史においては史上最高のプレイヤーの一人だった)の演奏能力を失ってから初めて発表されたアルバムで、深く沈みこむように落ち着いた雰囲気のもと、卓越した作編曲能力と鬼気迫る演奏表現力(このバンドではボーカルとギターを担当)が示されている。Virusは地下メタルシーンの最深部から出発しながらメタルを逸脱していくような方向性もあってリアルタイムでは妥当な評価を得ることができなかったが、いわゆる“アヴァンギャルドブラックメタル”の音進行面での定型確立に最も貢献したバンドの一つであり、その影響力は“不協和音デスメタル”周辺にまで及んでいる。再結成を果たしたVed Buens Ende...とあわせて今からでも注目を集めてほしいものである。
Ephel Duath:Through My Dog`s Eyes(2009)
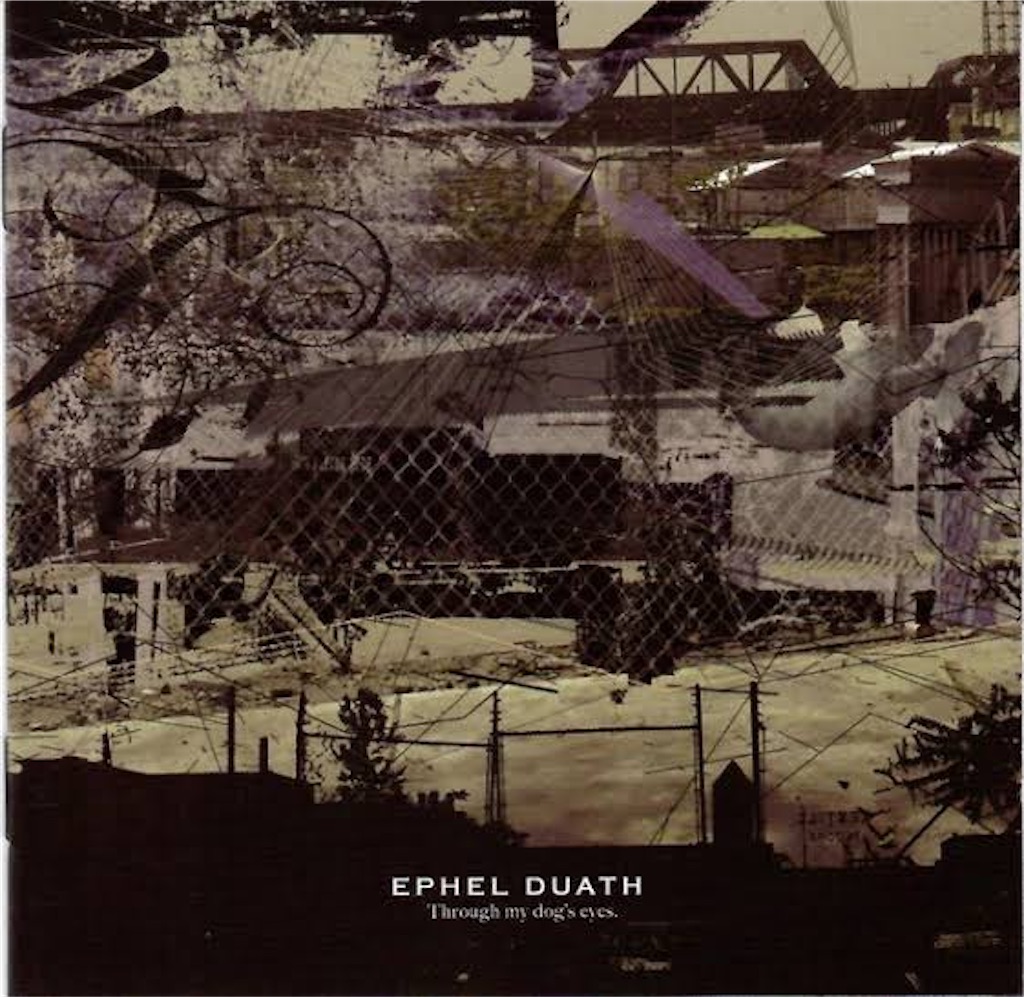
Ephel Duathはイタリアのブラックメタルシーン出身バンドで、ギタリストのDavide Tisoによるワンマンプロジェクト的な活動を続けていた。比較的よく知られているのが2005年にリリースされた3rdフル『Pain Necessary to Know』で、The Dillinger Escape Planをモダンジャズ風にマイルドにしたような入り組んだ展開のもと、Ved Buens Ende...系列とはまた質の異なるジャズ的コード感(60年代後半のモーダル/コーダル的なものをブラックメタル的イメージでまとめた感じ:ブラックメタルの定型そのものはあまりなぞらない)を掘り下げる音楽性は、同時期に注目度を増していったDeathspell Omegaなどと並べても見劣りしない(そして明確に毛色の異なる)素晴らしい個性を確立している。このアルバムの電子音響的な要素に焦点を当てて全体を再構築したリミックスアルバム『Pain Remixes the Known』(2007)のトリップホップ~ブレイクコア的な仕上がりはCar Bombなどにも通じるところがあるし、ブラックメタルシーン内ではある種キワモノとして知る人ぞ知る存在に留まっていたこのバンドは、今から振り返ってみれば“不協和音デスメタル”周辺の系譜にこそうまく位置づけられるのではないかとも思えてくる。とはいえそこからもさらに逸脱するのがEphel Duathの面白いところで、2009年に発表された4thフル『Through My Dog`s Eyes』では、メタル周辺領域を代表する超絶ポリリズムドラマーMarco Minnemanとの実質的なデュオ(Luciano George Lorussoのボーカルも要所で入るがインスト部分の方が多い)形態で極めて個性的なアンサンブルを構築。不穏な現代ジャズに近い音楽性はメタル系メディアでは殆ど注目されなかったが、Dan Weissのようなメタル影響下のジャズミュージシャンや、Imperial Triumphantに代表されるNYのジャズ~メタル隣接シーンに通じるものが多く、時代を先取りしていたオーパーツ的傑作として再評価すべき価値がある。Davideは現在Howling Sycamoreで“アヴァンギャルドブラックメタル+テクニカルスラッシュメタル”的な路線を開拓しており(ボーカルは元WatchtowerのJason McMaster)、それを理解するためにもEphel Duathを参照するのはとても意義深いことなのではないかと思われる。
Vektor:Outer Isolations(2011)

“プログレッシヴSFスラッシュメタル”としても知られるVektorは、ここ数年の“コズミックデスメタル”ブームの直接の起爆剤になったバンドだと思われる。最大の影響源の一つだというVoivod(バンドロゴのデザインは完全にVoivodを意識している)との音楽的な共通点は実はあまりなく、ギターリフやボーカルスタイルはDestructionのような欧州スラッシュメタルの系譜にあるものだし、コード感に関してもVoivodの特徴的な音進行傾向はほとんど引用しておらず、その後の世代であるObliveonやTimeghoulの方が直接的な類似点は多い。そうした音進行傾向をデスメタル以降のドラムスタイルで装飾し大曲構成にまとめ上げる音楽性は、ギター周りの軽さ重視のサウンドプロダクションは確かにスラッシュメタルではあるものの総合的にはOSDMリバイバル以降の“コズミックデスメタル”の方に近く、実際に影響を受けているバンドも多い。本作2ndフルは2009年の1stフルで注目を集めた上でその粗削りな部分を解きほぐし飛躍的な発展を成し遂げた大傑作で、新世紀の『Master of Puppets』とさえ言える素晴らしい完成度もあわせ、アンダーグラウンドシーンを越えた広い領域で高評価を獲得した。本稿に挙げたバンドは大部分が“知る人ぞ知る”ものばかりで、地下シーン内で影響を及ぼし合い音楽性を発展させてきた経緯はリアルタイムで並走するマニアでないかぎり把握しづらいのだが、Vektorはその枠を越えて知られる存在であり、後追い的に参照する際にも発見しやすいマイルストーンとして歴史に名を刻まれている。“不協和音デスメタル”方面への入門編としても優れた重要バンドである。
Mitochondrion:Parasignosis(2011)

Mitochondrionは2010年代以降に広く認知されるようになったカオティックなブルータルデスメタルの型を確立したバンドの一つである。暗黒宇宙を吹き荒れる大海嘯のようなデスメタルサウンドに関していえば、PortalやRites of Thy Degringoladeのような先駆者が2000年代前半の時点で概形を築き上げてはいたのだが、MitochondrionやAntediluvian(ともにカナダ出身)はそこにIncantationに代表される高速ドゥームデスメタルの分厚い重さを加え、漆黒の中に微かに星が瞬くかのような手応えのなさと足元に何かが粘りつく異様な安定感とを両立することに成功した。その聴き味はThornsやBlut Aus Nordのようなアンビエントなブラックメタルに通じ、Behemothなどが90年代後半に推し進めたブラックメタルとデスメタルの融合をブルータルデスメタル側から行ったような趣もある。本作2ndフルはそうした流れを象徴する記念碑的傑作で、最後を飾る完全アンビエントなトラック(メタル要素ゼロ)も含めアルバムの構成は完璧。楽曲構成には明確な展開があり慣れれば意外とわかりやすい魅力に満ちている作品だし、Portalに馴染めない場合はこちらから入ってみるのも良いのではないかと思われる。
Gigan:Multi-Dimensional Fractal-Sorcery And Super Sience(2013)

Gigan(名前の由来は東宝映画『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』)は、Gorguts『Obscura』の影響から出発して優れたオリジナリティを確立したものとしてはUlcerateなどと並び最初の世代とみていいバンドだろう。これは個人的な反省も兼ねての話なのだが、こちらの記事でまとめたように、初期デスメタルの混沌とした表現力を愛するリスナーはテクニカルデスメタルの技術点至上主義的な無味乾燥さを嫌う傾向があるし、テクニカルデスメタルやブルータルデスメタルの側からすると初期デスメタルの精神に訴えかけるドロドロした歪みを好まないきらいがある。『Obscura』リリース当時の反応に否定的なものが多かったというのは、ガワはテクデス/ブルデス的だったのに芯の部分では表現志向が強く、両方の要素を徹底的に突き詰めた音楽性がリスナーの許容範囲を超えていたというのが大きいのかもしれない。自分は完全に初期デスメタル派で、メカニカルで無味乾燥なテクデス/ブルデスは(それだからこその気楽な心地よさがあることも承知しつつも)あまり面白く聴けない傾向がいまだに残っているのだが、そういう立場でもGiganのようなバンドには2010年頃の出現当時から惹かれていた。本作3rdフルはバンドのオリジナリティが自分のようなタイプのリスナーにもわかるくらい明確に確立された傑作で、『Obscura』の複雑なコード感をいわゆるSci-fiメタル方面に発展させた音進行感覚が素晴らしい魅力を発揮している。リーダーであるEric Hersemannは『Obscura』を崇拝する一方でマイルス・デイビス(70年前後のいわゆる電化マイルス期)やチャールズ・ミンガス、Captain BeyondやRush、フランク・ザッパやPrimusなどから影響を受けているとのことで、それを踏まえて本作を聴くと、奇怪で楽しげなノリやコード進行は確かにPrimusに通じる部分が多く、他のデスメタルにはない味わい深い個性になっているように感じられる。宇宙的なテーマや演出はTimeghoulやVektorを想起させはするがそれらとは別の文脈から登場したバンドであり、いわゆる“コズミックデスメタル”と比較することはできるもののやはり区別して吟味されるべき音楽なのだと思う。このように、テクデス的なスタイルの良いところのみを抽出(というかつまらなくないテクデスのみを下敷きに発展)しそれを土台にオリジナルを構築する世代が出現すると、それをさらに発展させ独自の興味深い個性を確立できる後続も自然と増えていく。そうした流れを示す存在としても重要なバンドである。
Kayo Dot:Hubardo(2013)

Kayo Dotはmaudlin of the Wellがさらなる音楽的拡散を意図し発展的解散・改名したことにより誕生したバンドで、メタル的な要素も残しつついかなる領域にも接続する音楽性は、このジャンルから発生したあらゆる音楽の中でも最も魅力的な豊かさを湛えている。現在も在籍する唯一のオリジナルメンバーであるToby Driverは、Tiamatの知る人ぞ知る傑作『Wildhoney』をはじめとする欧州ゴシックメタルやUlverの脱ジャンル的活動に魅了されて音楽活動を始め、マサチューセッツ州ボストンを拠点としたmaudlin of the Wellでは様々なポストロック~インディーロックと交錯する特殊メタルの傑作群を発表。2003年にKayo Dotに移行してからはニューヨークを拠点とし、当地の越境的ミュージシャンとの交流を通してメタルに留まらない異形の作品を生み出し続けてきた。本作『Hubardo』はそのひとまずの集大成と言えるアルバムで、motW以来となるデスメタル的なエッジと室内楽ジャズオーケストラ的な管弦アレンジを融合する作編曲が最高の仕上がりをみせている。10分超の大曲も4つ含む全100分の長尺を難なく聴かせきるアルバム全体の構成は完璧で、巨大で奇怪な印象に満ちているのに吞み込みづらさは全くない。本稿のタイトルに掲げた“不協和音エクストリームメタル”を最も体現する不世出の傑作である。
Kayo DotやToby Driver関連作品(Vauraやソロなど音楽的な振り幅は無尽蔵)を聴いていて考えさせられることの一つに「新しい音楽をプログレッシヴと呼ぶのはそろそろやめようぜ」というものがある。この記事のAzusaの項でもふれたように、既存のフォームを打ち破ろうとする姿勢を指していう「プログレッシヴ」と、そうした音楽に影響を受けたバンド群が確立した定型的音楽スタイルを指していう「プログレッシヴ」とは、字面は同じでも意味合いは異なり、革新と保守という立ち位置について言えば真逆とすら言える違いがある(しかも後者は保守なのにもかかわらず革新のイメージを利用しているきらいがある)。“プログレッシヴメタル(プログメタル)”や“プログレッシヴデスメタル(プログデス)”という言葉も、特定の音楽性を明確に指し示すのでそれを語るにあたっては重要だが、一見それ風に見えるけれども実は別の文脈から出てきている音楽(例えばGorgutsの系譜は“プログメタル”や“プログデス”に含まれないはず)を括るのは筋違いだし、30年近く前に生み出されたそうした言葉を用いて新しい音楽を語るのも、規格外に豊かなものを古く漏れの多い概念に押し込むようなことであり適切な姿勢ではないだろう。大事なのは批評言語の更新または創出であり、それにあたっては様々な要素を一般論に括らず丁寧に精読していく姿勢が必要になる(Kayo Dotのような豊かすぎる音楽に対しては特に)。本稿がそれにあたっての見取り図や足掛かりになれば幸いである。
Morbus Chron:Sweven(2014)

2010年代の初期デスメタルリバイバルにおける記念碑的傑作である。90年代前半までのいわゆる初期デスメタルが多分に備えていた混沌とした表現力を愛するファンはこれ以前も根強く存在し、テクニカルデスメタル~ブルータルデスメタル~スラミングデスメタルといった技術&過激志向が一段落する2000年代中盤には初期デスメタルならではの生々しく豊かな滋味に再び注目が集まり始めていたのだが、リバイバルの参照元を超えるオリジナリティを獲得するバンドは稀で、ムーブメントとしてのパンチというか、注目する価値があると説得するだけの存在感は今一つだったようにも思われる。それが2010年代に入ると、初期デスメタルの様々なスタイルを参照しつつ独自の配合で組み合わせることにより新たな個性を生み出してしまう優れたバンドが明らかに増えてきた。Morbus Chronはその代表格で、最終作となった本作2ndフルでは過去の歴史的名盤群に勝るとも劣らない神秘的な深みが具現化されている。Autopsyのようなドゥームデスからスピードメタル~NWOBHMを経由してブラックメタルに接続するようなスタイルは既存の様々な要素をモザイク状につなぎ合わせたような仕上がりだが、起伏が多く唐突な展開が散見されるもののぎこちなさは不思議となく、「夢」を意味するアルバムタイトルに非常によく合っている(というかこういう解釈をすることで初めて理解の糸口が得られるタイプの作品なのだと思う)。ジャンルの歴史が回顧的に想起されそこから新たなものが生まれてくる瞬間を捉えた本作は、そうした音楽構造が示す批評性の面でも、そうしたことを意識しなくても心に深く染み入る只ならぬ雰囲気表現力の面でも、文字通りの“歴史的”名盤なのだと言える。
なお、Voivod的な成分を含みインナースペース的な音響表現をしていることもあってか“コズミックデスメタル”に通じる印象もある本作だが、TimeghoulやNocturnus、ObliveonやVektorのような系譜とはおそらく別のところにある作品で、その枠に括るのは不適切な気もする。しかし、本作に影響を受けたと思われるバンドがコズミックデスメタル的な音楽性を志向し、それがそのスタイル名で形容される展開が少なからず生じているのをみると、そういう細かい分類にこだわるのは些末で野暮なことにも思える。現代デスメタルシーンを考えるにあたっての重要作品の一つというくらいに考えておくのがいいのかもしれない。
Dodheimsgard:A Umbra Omega(2015)

Dodheimsgardはノルウェー以降のブラックメタルの発展史を単独で体現するバンドである。そもそもノルウェーのブラックメタルシーン(それ以前のスラッシュメタル近傍のブラックメタル=1st Wave of Black Metalと区別するために2nd Wave of Black Metalと呼ばれる)というのは、たまたまメタルを主題としているだけで音楽的には何でもありの豊かな領域で、このジャンルを立ち上げた筆頭バンドMayhemが1987年に発表した公式初作品『Deathcrush』冒頭にはコンラッド・シュニッツラー(Tangerine Dreamなどで知られるジャーマンロック~電子音楽の代表的音楽家)の音源が使われていたり、黎明期の最重要バンドというかソロユニットの一つBurzumはそのままミニマル音楽に接続する作品群を発表していたりと、ジャンル越境的な志向を持った天才達が“他人と被ったら負け”精神のもと鎬を削っていた。ULVERはその最大の好例だし、このジャンルの一般的なイメージを示すプリミティヴブラックメタルにしても、後続がそれを模倣し厳格に守る対象としたためにワンパターンな印象ができてしまっただけで、Darkthroneが雛形を作りだした時点ではそれまでにない斬新な音楽スタイルだったのである。Ved Buens Ende...でギターを担当するVicotnikも同シーンの筆頭的天才として語られるべき奇才で、様々な楽器を使いこなす演奏表現力と卓越した作編曲能力をもってカルトな傑作を発表し続けてきた。
DodheimsgardはそのVicotnikが率いるバンドで、各作品に参加したミュージシャンの豪華な一覧はノルウェーシーンにおける梁山泊のようでもある。1995年の1stフル『Kronet till konge』はDarkthroneの名盤3部作(1992~1994年)を模倣せず発展させるようなプリミティヴブラックメタルの傑作、1996年の2ndフル『Monumental Possession』はノルウェー以降のブラックメタルに1st Wave Black Metal的なスラッシュメタルを掛け合わせたブラックスラッシュの傑作(そのスタイルの誕生を告げるAura Noirの名盤1stフル『Black Thrash Attack』と同年発表)。そこからシンフォニックブラックメタルに接近した1998年の名作EP『Satanic Art』に続く1999年の3rdフル『666 International』はブラックメタル史を代表するカルト名盤で、アヴァンギャルド方面のブラックメタルを代表する名人のみで構成されたメンバーがインダストリアル~トリップホップ領域にも闖入する音楽的実験の限りを尽くしている。その路線を拡張しつつ少し焦点を見失った感もある2007年の4thフル『Supervillain Outcast』を経て長い沈黙ののち発表したのが2015年の本作5thフル『A Umbra Omega』であり、ここではVed Buens Ende...やVirus(リーダーのCarl-Michaelは『666 International』で極上のドラムスを披露している)に通じる“アヴァンギャルドブラックメタル”系統のコード感覚がそのオリジネーターにしか成し得ない形で高度に発展されている。冒頭曲を除けば全曲が10分を超える6曲67分の長さを難なく聴かせきるアルバム全体の構成は見事の一言で、変則的な展開の一つ一つに異様な説得力がある。聴いた者からは軒並み高い評価を得ている本作は“不協和音デスメタル”周辺のミュージシャンがインタビューで名前を挙げることも多く、カルトな立ち位置の作品ではあるが現代のシーンへの影響力は少なくないように思われる。マニア以外には上記のような広がりが意外と知られていないブラックメタルというジャンルを理解するにあたっても必須の存在だし、今後この人脈から生まれるだろう傑作の数々に備えるためにも、ぜひ聴いてみてほしいバンドである。
Plebeian Grandstand:False High, True Lows(2016)

不協和音を用いた表現を追求するエクストリームメタルの流れにおいて重要なトピックの一つに、ハードコアとブラックメタルの影響関係がある。Mayhemの歴史的名盤『De Mysteriis Dom Sathanas』(1994年)収録の名曲「Freezing Moon」の執拗な半音上下往復パートに顕著な、ブルース的な反復(解決せずに行きつ戻りつする展開)が欧州スラッシュメタルとジャーマンロック~現代音楽などを通過することで確立されたミニマル感覚は、メタルとハードコアの音進行傾向の結節点として以降の音楽全域に絶大な影響を与えた。アンダーグラウンドメタルのマニアとして知られるサーストン・ムーア(Sonic Youth)はMayhemのパーカーを愛用する写真があるようにこのジャンルの紹介に熱心で、そこ経由でアメリカのアンダーグラウンド〜インディシーンにおけるブラックメタルの注目度が高まったというのもあるだろう。Convergeが2001年の歴史的名盤『Jane Doe』の頃からブラックメタルの要素を大きく取り込んでいく流れをみてもわかるように、ハードコアの楽曲構造や衝動重視の演奏表現とブラックメタルとは音楽的に非常に相性が良く、思想的な面では水と油でシーン的な交流は活発ではなかったと思われるが(National Socialist Black MetalとAnti-fascist Hardcoreの対比など)、録音作品を通しての影響関係は水面下でかなり密に構築されてきたのではないかと思われる。ここで重要なのがハードコアからブラックメタルへの影響で、Converge系統のカオティックな不協和音の感覚はそれ以前のブラックメタルにはなかったのが、ブラックメタル要素を取り込んだハードコア作品における達成を逆輸入する形で、新たにブラックメタル側にも流入するようになった印象がある。Deathspell Omegaはそうした展開における最重要バンドの一つで、2000年代には上記のような配合を成し遂げたブラックメタル関連バンドが急増した。こうした交流(というよりも盗み合いという方が近いかも)が2010年代以降のAlcestやDeafheavenのような越境的影響関係を隠さないバンドの出現を準備した面もあっただろう。メタルの枠内を見ているだけでは現代メタルシーンの実情はつかめないということをよく示す話だと思う。
Plebeian Grandstandはフランス出身のバンドで、ハードコアシーンに所属しながらもブラックメタルの要素を積極的に取り込む活動を続けてきた。本作3rdフルはその傾向が一気に高まった傑作で、「Deathspell Omegaをカオティックハードコア化した感じ」と言われるような感触も確かにあるのだが(Spotifyのプレイリスト「Deathspell Omega Like but Not Nazis」に入れられていたりもする)、音進行の微細な配合や演奏感覚はやはり異なるし、その上で優れた個性を確立している。一般的にはほぼ無名だが、“不協和音デスメタル”のバンドがインタビューで名前を挙げることが多く、地下シーンではかなりの影響力を持っていることが窺われる。それも頷ける強力な作品だし(終盤にハイライトが続く構成が素晴らしい)、聴いておく価値は非常に高いと思われる。
Chthe'ilist『Le dernier crépuscule』2016

Demilichの項でふれた「素材としてそこに様々なものを付け加えやすい音楽性」「単旋律のリフに肉付けするコードの質によって様々に異なる表情を描くことができる“素材としての自由度”」を最もよく体現するバンドの一つ。現時点で唯一のフルアルバムである本作はDemilichをDisincarnate経由で中期Emperor(2nd~3rdあたり)と融合したような音楽性で、リフまわりの変拍子やストップ&ゴーの入れ方は笑えるくらいDemilichそのものなのだが、その並びやコード付けから生じる総合的な音進行感覚は明確に異なり、参照元の魅力を格段にわかりやすく引き出している点においてこちらの方が好きだと感じる人も(面倒くさいマニアの中にも)多いのではないかと思われる。初期デスメタルの理想を体現する2010年代屈指の傑作である。
本作に関連して注目しておきたいのが現代デスメタルシーンにおける兼任バンドの多さである。Chthe'ilist のリーダーであるPhillippe Tougasはフューネラルドゥーム寄りバンドAtramentusも運営(2020年発表の1stフル『Stygian』は同年屈指の傑作)、Zealtoryの名盤『The Charnal Expanse』(2013)に貢献しFunebrarumやVoidceremonyにも参加するなど、現代デスメタル周辺シーンを代表するバンドの多くに関与し、個性的な傑作を連発している。Metal Archivesの兼任バンド一覧ページを漁るだけでも興味深い作品が大量に見つかり、その豊かさに驚かされつつさらなる深みにはまっていくことができる。シーンを網羅的に把握するにあたってはまずこうしたキーパーソン(Phillippe以外にも多数存在)を探し出すのが良いのではないかと思う。
ちなみに、本作の末尾を飾る「Tales of the Majora Mythos Part Ⅰ」は『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』を題材にしている模様。そもそもDemilichという名前の由来が『ダンジョンズ&ドラゴンズ』であり(ルールブックにあった単語を採用したとのこと:『Nespithe』20周年記念盤ブックレットのインタビューより)、Tomb Moldをはじめとする多くのバンドが『Dark Souls』シリーズにインスパイアされているという話を聞くと、非日常的な世界観表現を重視するデスメタルのような音楽において、ダークファンタジー方面のゲームが重要な主題になっているという傾向は確かにあるのではないかと思える。コズミックデスメタルの流行もそれと切り離して語れるものではない気もするし、ゲームとエクストリームメタルの両方に精通した識者の話を伺いたいところである。
Imperial Triumphant:Vile Luxury(2018)

Imperial Triumphantはニューヨークを拠点に活動するテクニカルなブラックメタル出身バンドで、初期は19世紀クラシック音楽の和声感覚を複雑な曲構成のもとで繰り広げるタイプの比較的オーソドックスな音楽をやっていた。そこから大きな路線変更がなされたのが2015年の2ndフル『Abyssal Gods』で、創設者/リーダーであるZachary Ilya Ezrin(Cal Artsで作曲の学位を得たクラシック音楽寄りプレイヤー)、2012年に加入したKenny Grohowski(New Schoolでジャズ・パフォーマンスの学位を得たドラマー、ジョン・ゾーン人脈のキーパーソン)、そして2015年に加入したSteve Blanco(Suny Purchaseでジャズ・パフォーマンスの学位を得たベーシスト、ジャズ方面ではむしろピアニストとして有名)というトリオ編成になったことで楽曲構造が大幅に複雑化。それをうけて制作された本作3rdフル『Vile Luxury』は、Gorguts系統の現代音楽寄りデスメタルを40~60年代ジャズ(プレモダンからモーダル/コーダルまで)のコード感とブラックメタル+ジャズ的な演奏表現で悪魔改造したような音楽性で、入り組んだ展開をすっきり聴かせる驚異的な構成力もあって様々なメタル系メディアの年間ベストに選出されることになった。メンバーが特に影響を受けたというジャズのアルバムは、マイルス・デイビス『Nefertiti』、ジョン・コルトレーン『Interstellar Space』、セロニアス・モンク『Monk`s Dream』、デューク・エリントン『Money Jungle』、ベン・モンダー『Hydra』で、確かにこの5枚の和声感覚や静謐かつハードコアなアンサンブル表現、そして複雑な変拍子遣い(例えば「Lower World」はそのまま『Hydra』に通じる)を足し合わせれば『Vile Luxury』になると言ってしまえる感もある。壮大ながら柔らかい肌触りもあるシンフォニックなサウンドは金管プレイヤー5名やYoshiko Ohara(Bloody Panda)のような現地の優れたミュージシャンを多数招いたからこそ実現できたものでもあり、KralliceのColin Marstonによる素晴らしい音作りなどもあわせ、NYという地域の特性が様々な面において反映されたものだと言える。事実、バンド自身にとってもNYは音楽表現における主要なテーマであるようで、2020年に発表された4thフル『Alphaville』に関するインタビューでの質問「『Vile LuxuryはNYへのオマージュだったが『Alphaville』はそのテーマの延長線上にあるものか』と問われたIlyaは、「ある意味ではね。我々はNYのバンドだし、曲の多くはNYの街をテーマにしている。自分が知っていることを書くのが一番だと思うし、ここは自分の人生の中で一番の故郷なんだ」と答えているし、別のインタビューでも、「Imperial Triumphantの音楽はNYの活気と威厳からどれほどのインスピレーションを得ているのか」と訊かれて、「活気と威厳、そしてその下にある不潔さと腐敗からインスピレーションを得ている。観光客でも認識できる刺激的な二面性があり、我々はそれを自分達の音楽に可能な限り反映させようと試みている」と答えている。このシーンにおける現代メタル-ジャズ間越境の象徴ともいえる立ち位置にいるバンドなのである。
なお、Imperial Triumphantの前任ベーシストErik Malaveは現Pyrrhon(Seputusにも所属)、前任ドラマーのAlex Cohenも2015年までPyrrhonに在籍し卓越した演奏表現力を披露していた。Kenny GrohowskiはImperial Triumphantでの活動の傍らPyrrhonのライヴドラマーを務めていたこともあるし、人脈的繋がりはかなり密接なものがある。NYのシーンは今後メタルシーン全体に無視できない影響(特にジャンル外との越境的交流傾向)を生んでいくだろうし、Kayo Dotなどもあわせ、このあたりのバンドに注目しておく価値は非常に高いのではないかと思われる。
Inter Arma:Sulphur English(2019)

本稿に挙げたバンドはいずれも唯一無二の個性を確立しているものばかりで、こうした「1バンド1ジャンル」的な様相を見ていると、よく言われる「メタルは様式美に縛られた音楽でいつまでも同じようなことを繰り返している」という定説は実情を全く反映していないようにも思えてくる(“様式美”にもいろいろあり時代によって変遷していくのだということはこの記事でも詳説した)。しかし、それはアンダーグラウンドな世界の話であり、こちらのインタビューでも述べられているように、保守的で変化を好まない気風はいまだに多くの部分に残っている。Inter Armaはそうした風潮に真っ向から対立するバンドで、別項でふれたNYシーンなどとはまた異なる方向性での越境的発展を積極的に繰り返している。2020年発表のカバーアルバム『Garbers Days Revisited』には、Ministry、ニール・ヤング、Cro-Mags、Nine Inch Nails、Husker Du、Venom、Tom Petty & The Heatbreakers、プリンスの楽曲が収められており、ブルースやカントリー、ファンク~ブラックロック、ハードコアとスラッシュメタル、それらと隣接するインダストリアルメタルといったジャンル的振り幅は、このバンドの複雑な音楽的広がりをとてもよく説明してくれているようにも思われる。2019年の4thフル『Sulphur English』はMorbid AngelとNeurosisを混ぜてエピックメタル経由でPink FloydやCSN&Y(Crosby, Stills, Nash & Young)に接続するような音楽性で、所々で顔を出すGorguts的コード感にアメリカ音楽の豊かなエッセンスが加わったような出音は極上の滋味に満ちている。Sleep『Dopesmoker』あたりに通じるマッシヴなロックグルーヴも素晴らしく、他の多くの“不協和音デスメタル”では得られない手応えを与えてくれるように思う。メタルを音楽史に位置付けなおしつつ発展させる系譜の急先鋒としても重要なバンドの一つである。
詳しくはこちら
Tomb Mold:Planetary Clairvoyance(2019)

Morbus Chronの項でもふれたように、2010年代に入ると、初期デスメタルの様々なスタイルを参照しつつ独自の配合で組み合わせることで新たな個性を生み出してしまうバンドが明らかに増えてきた。ジャンルのマニアとしての博識を備え、参照対象の特性を深く理解しそれらの美点や自分達自身との違いを把握しているために、この程度の使い方では新たな味わいは出せないという厳しい基準が備わり、それを超えるための入念な練り込みを通して独自の音楽性を確立することが可能になる。Tomb Moldはその点において現代メタルシーンを代表する存在であり、2015年の結成当時からこのジャンルの歴史に残る傑作を連発してきた。このバンドが凄いのはハイコンテクストさとキャッチーさの両立が極めて見事なところで、様々な名盤を聴き込んだ経験と文脈把握がなければ読み込めない部分が多い一方で、そういった知識がなくても直感的に楽しめる訴求力にも満ちている。2017年1stフル『Primordial Malignity』はPestilenceやBolt Thrower、2018年2ndフル『Manor of Infinite Forms』はDemilichやAutopsyにも通じるスタイルというように比較対象を挙げることは難しくないが、全てのフレーズが高度に捻り解きほぐされ、何かの亜流といった次元を遥かに超えた個性を身につけている。2019年の3rdフル『Planetary Clairvoyance』はそうした蓄積を踏まえつつ新たな味わいを確立した大傑作で、DemigodやRippikouluのようなフィンランド型ドゥームデスを土台としつつ、TimeghoulやVektor、Morbus Chronといった先達とはまた異なる“コズミックデスメタル”的な世界観表現を達成。各楽曲の構成はもちろん全体の流れも一続きの物語のように美しくまとまっており、各リフの強力さ(ミクロ)の面でもトータルアルバムとしての完成度(マクロ)の面でもデスメタル史上最高傑作の一つなのではないかとすら言える。くぐもり気味の音質は個人的にはそこまでツボではないが(そういう音質自体はデスメタルによくあるので問題ではないのだがくぐもり方の質がやや合っていない気もする)、微妙に細部が聴き取りにくいために繰り返し取り組みたい気にさせる絶妙な仕上がりも含め、これはこれでうまく機能しているように思う。初期デスメタルリバイバルの最高到達点の一つとしてぜひ聴いてみてほしいアルバムである。
それにしても、ここまで見てきて改めて実感させられるのがカナダシーンの凄さである。Voivod、Obliveon、Gorguts、Martyr、Mitochondrion、Chthe`ilist、Tomb Moldという名前の並びはメタルの歴史全体を見回しても屈指のラインナップなのに、デスメタルの中心地としてよく語られるアメリカや北欧に比べ、カナダは地域単位では注目される機会が少なかったように思う。本稿で体系的に示したように先鋭的なメタルの系譜において非常に重要な役割を果たしてきたシーンだし、正当な評価を得る機会が増えてほしいものである。
Titan to Tachyons:Cactides(2020)

Titan to Tachyons はOrbweaverやGiganといった“不協和音デスメタル”的バンドに参加してきたギタリストSally Gatesが結成したインストゥルメンタルの“avant-rock/jazz metal”バンドで、ドラムス担当のKenny Grohowski(Imperial Triumphant)およびベース担当のMatt Hollenberg(Cleric)からなる。KennyとMattはジョン・ゾーン楽曲を本人から委託され演奏する直系バンドSimulacrumのメンバーでもあるわけで、Titan to Tachyonsはニューヨークのジャズ~メタル越境シーンをジャズ寄りに体現する存在といえる。本作は2020年に発表された1stフルで、音楽性を一言でまとめるなら、GorgutsやEphel Duathのような現代音楽寄り和声感覚をもつエクストリームメタルの語彙を用いてKing Crimsonの『Starless And Bibile Black』と『The ConstruKction of Light』の間にあるような渋く複雑なアンサンブルを繰り広げる、という感じだろうか。楽曲構成は作曲と即興のミックスで、Sallyが全曲をギターで作曲した上で他の2名が各自のパートを追加、そこからさらにスタジオでのジャムセッションでアイデアを拡張していったとのこと。その結果、細部まで緻密に書き込まれた作り込みと勢いある閃きが自然に両立され、異形ながら艶やかな構造美が生み出されている。ドラムスのフレーズや各楽器のサウンドプロダクションは明らかにメタル寄りだが、全体的な聴感はむしろ現代ジャズに近く、メタルを全く聴かないそちら方面のリスナーにも訴求する仕上がりになっていると思われる。3名がそれぞれ関与してきたエクストリームメタルの技法が随所で駆使されているのに音作りを柔らかめにすればラウンジジャズとしても通用するような落ち着きぶりがなんとも不気味で(『ツイン・ピークス』シリーズに強くインスパイアされているとのこと)、そうした力加減が得難い個性にも繋がっている。直接的な関係はなさそうではあるがEphel Duath『Through My Dog`s Eyes』の発展版としても聴ける非常に興味深い音楽。傑作だと思う。
ここから先は今年発表のアルバム。いずれも驚異的な作品だが、現時点では聴き込みが足りない(各々10回以上聴き通してはいるが時間経過の面で十分でない)ことも鑑みて紹介コメントは簡潔なものに留めておく。
Ad Nauseam:Imperative Imperceptible Impulse(2021)

イタリア出身。本作は5年ぶりのリリースとなる2ndフルアルバムで、ストラヴィンスキーやペンデレツキのような現代音楽寄り作曲家、アンダーグラウンドメタルの名バンド群、その他多岐に渡る影響を消化した上で、GorgutsやUlcerateを参照しつつその先の世界を切り拓くような高度な音楽性を構築している。なにより驚異的なのは音響で、スティーヴ・アルビニを崇拝し理想の環境を作り上げるために自前のスタジオを建てたという蓄積のもと、イコライザーやコンプレッサーを殆ど使わない録音作業を膨大な時間をかけて完遂したという。爆音と過剰な手数を伴うデスメタルスタイルでそうした手法を成功させるというのはとても信じ難い(つまり演奏技術からして常軌を逸するレベルで凄いという)ことだが、本作の異様な音の良さを聴くと確かに納得させられるものがある。同様の音楽性を志向するミュージシャンの間では既に高い評価を得つつある(インタビューで名前が挙がることが少なくない)し、稀有の傑作としての定評がこれから固まっていくのではないかと思われる。
Siderean:Last on Void`s Horizon(2021)

スロベニアのSci-FiメタルバンドTeleportが改名し遂に完成させた(本来は2019年後半リリース予定だった)1stフルアルバム。Teleportの頃はVektorやVoivodあたりのプログレッシヴなスラッシュメタルをGorguts的な無調寄りデスメタルと組み合わせるスタイルを追求していたが、本作ではDodheimsgardやEphel Duathに通じるアヴァンギャルドブラックメタル的な音進行が大幅に増加。スラッシュメタルならではの軽く切れ味の良い質感を保ちつつ複雑なリフをキャッチーに聴かせる音楽性は、VirusとVektorを理想的な形で融合するような趣もあるし、Howling Sycamoreあたりと並走する意外と稀なスタイルでもある。6曲40分のアルバム構成も見事な傑作である。
Seputus:Phantom Indigo(2021)

Seputusは3人全員がPyrrhonのメンバーだが(そちらのリーダーと目されるDylan DiLellaのみ不在)、テクニカルデスメタル形式を土台にしながらもPyrrhonとは大きく異なる音楽性を志向している。神経学者オリバー・サックスの著書『Hallucinations』(邦題:見てしまう人びと 幻覚の脳科学)を主題に5年かけて作り上げられたという本作2ndフルは、Gorguts『Colored Sands』あたりの不協和音デスメタルをDeftones経由でNeurosisに繋げたような音楽性で、何回聴いてもぼやけた印象が残る(“焦点が合わない具合”が安定して保たれる感じの)特殊な音響構築のもと、驚異的に優れた作編曲と演奏表現で走り抜ける作品になっている。この手のスタイルにしては不思議な明るさが嫌味なく伴う音楽性は代替不可能な魅力に満ちており、“不協和音デスメタル”の系譜のもと新たな世界を切り拓く姿勢が素晴らしい。個人的にはPyrrhonよりもこちらの方が好き。今年を代表する傑作の一つだと思う。
Emptiness:vide(2021)

ベルギーのブラックメタル出身バンド、活動23年目の6thフルアルバム。元々はアヴァンギャルドブラックメタル的な音楽性だったのだが、2014年のインタビューで「最近の好み」としてLustmord、MGMT、コナン・モカシン、ワーグナー、Beach House、ジャック・ブレル、デヴィッド・リンチ的なもの、Portisheadなどを挙げているように、メタルの定型的なスタイルからためらいなく離れる志向を早い時期から示していた。まだメタル要素をだいぶ残していた2017年の5thフル『Not for Music』から4年ぶりに発表された本作は、ポータブルレコーダーを持ち歩きながら様々な場所(森の中や街頭、屋根裏など)で録ったという音源をスタジオ録音部分と組み合わせて作られた(メタル要素はほとんどなくむしろポストパンクに近い)作品で、様々に揺らぐ距離感や残響の具合が交錯し焦点を合わせづらい音響が複雑な和声感覚と不可思議な相性をみせている。楽曲や演奏の印象を雑にたとえるならば「スコット・ウォーカーやシド・バレットとベン・フロストをPortishead経由で融合したような暗黒ポップス」という感じだが、総合的なオリジナリティと特殊で特別な雰囲気(アブノーマルだが共感させる訴求力も濃厚に持ち合わせている)は他に比すべきものがない。DodheimsgardやVirus、Fleuretyなどの代表作に比肩する一枚であり、本稿でまとめた系譜から生まれつつそこから躊躇いなく飛び立つものでもある。どちらかと言えばメタルを知らない人にこそ聴いてみてほしい、奇怪なポップスの大傑作である。